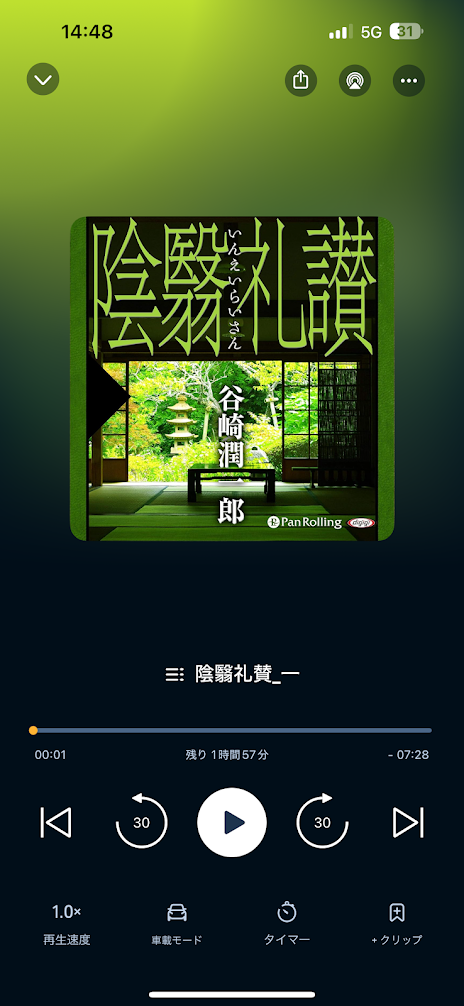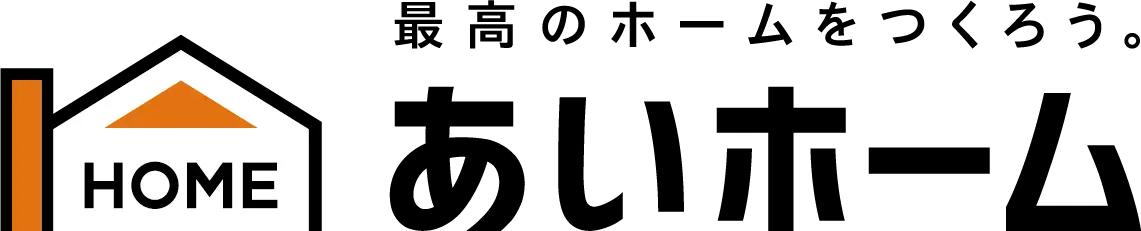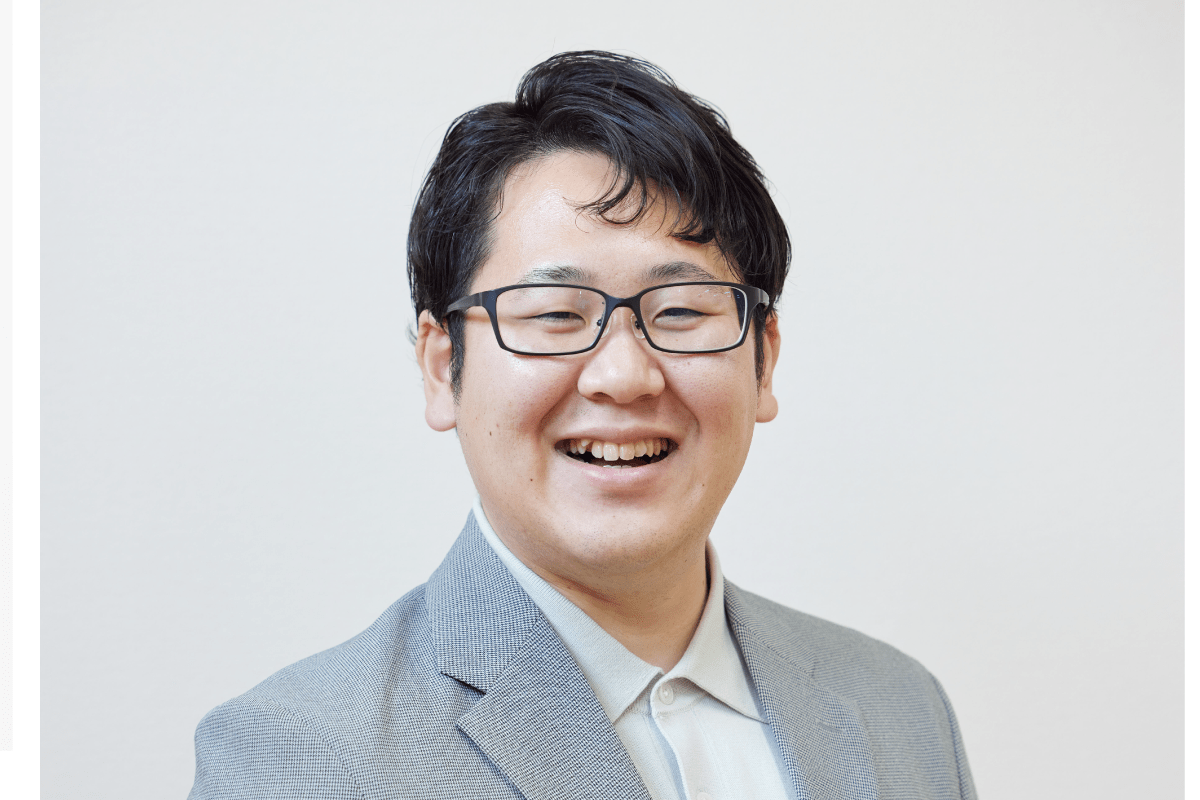こんにちは、設計の鈴木です。
今回は最近読んだ(聞いた)本について書かせていただきます。
今回のブログタイトルがまさしく読んだ本の題名ですが、「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」
という谷崎潤一郎さん著の本を聞きました。
1933年とおよそ100年ほど前に書かれた本ですが、大学時代にお世話になった教授が読まれていた本だったので特に事前情報なしに聞いてみました。
昭和8年頃の日本の様々な文化について著者の視点から見た感想や思いを述べている本で、建築、芸能、食器などについて書かれています。
タイトルの「陰翳」という字にあるように、いずれも影という部分に焦点をあてて書かれており
読んだ感想として一番に感じたのは、圧倒的な懐古主義というべきか純和風主義というか、日本人の感じる風情とはかけ離れた文化に対する著者の熱い気持ちを感じました。
その中でも特に印象に残ったのが、照明についてのお話で、執筆当時もランプや蠟燭から照明器具に移り変わっていき、電灯でお部屋のすべてが明るく照らされていることを嘆いていた部分で、ちょうど先日、大光電機株式会社さんのショールームを見学させていただき、照明計画やライティングシミュレーションを体験させていただいたので、実体験とも重なり印象に残りました。
実際、照明計画というのは住宅の計画の中でもかなり重要な部分で、迷われたら実際にショールームに行ってみることをおすすめいたします。
実際に体験してみて、今までの感覚だと明るすぎたかもしれないということを体感しました。
およそ100年前の本にはなりますが、100年経過した今だからこそ執筆当初よりも色濃く本の内容を感じることができ日本文化の良さについて思い返すきっかけとなりました。
もし、お暇で本を手に取ることがあれば、お家の照明を改めて見直してからこの本を読んでいただけると照明に関する意識が少しだけ変わるんじゃないかなと思います。
それでは、また。